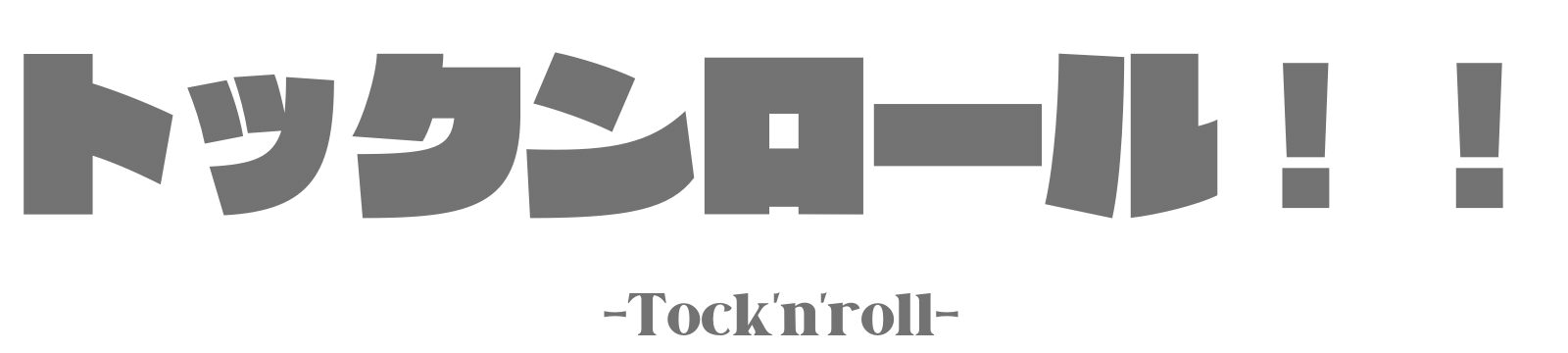- 「エレキベースにはどのチューナーを使ったら良いのかわからない」
- 「せっかくチューナーを買ったのにエレキベースの音を拾ってくれない」
ベーシストの方なら、一度はそんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。
今回はそんな悩みを解決してくれる「ベースチューナー」について、人気のベースチューナーからクリップ型・ペダル型の違いなど解説していきます。
ベースチューナーとは
チューナーの中にはエレキベースだと音が低すぎて、なかなかチューニングがしにくいものも存在します。
ベースチューナーとは、そんな音域の低いエレキベースでもしっかりと音を拾ってくれるチューナーを指します。
特にチューニングにはまだ慣れていない初心者の方にとっては、良いベースチューナーを使うことが上達の近道になることも。
ベースチューナーを使うメリット
正しい音程を把握できる
ベースチューナーを使う一番のメリットは、エレキベースの正しい音程を把握できることです。
きちんと正しい音程で曲を弾くことができれば、弾いている方も聞いている方も心地が良いもの。
常に正しい音程で演奏するためには、できれば1曲ごとにチューニングをする癖をつけたいですね。
チューニング時間が短縮できる
ベースチューナーを使うとチューニング時間が短縮できるのもひとつの大きなメリットです。
低い音に反応しにくいチューナーだとチューニングに時間がかかってしまいますが、ベースチューナーを使えばその分の時間を練習に充てることが出来ますよね。
ベーシスト向きの機能がついていることも
またベースチューナーは機種によって、プラスアルファのベーシストが使いやすい機能が付いていたりします。
練習に使用できる「メトロノーム機能」やテンポキープの練習になる「テンポ検出機能」がついているものなどを使用すれば、演奏技術の向上にも役立てることができそうですね。
ベースチューナーを使うデメリット
値段が張る
ベースチューナーは感度が良いものでないと機能しづらいため、やはり相応の値段が張ることが多いです。
とはいえ必要最小限の機能に絞ればそれなりに手頃なベースチューナーもあるため、チューニングに自信がある方はシンプルな機能ものでも良いかもしれません。
音感が鍛えられにくい
ベースチューナーはとても便利ですが、あまりに頼りきりになってしまうと音感が鍛えられにくくなってしまいます。
音感を鍛えるには日頃からベースチューナーを使ってチューニングをした後でも、バンドや曲に音程があっているか常に意識するようにしましょう。
安いのが使えなくなる
一度しっかりとエレキベースの音を拾ってくれるベースチューナーを使用すると、安すぎるチューナーが使えなくなってきます。
あまりに安いものだと、使いづらくて結局ベースチューナーを買い直すはめになることも。
ベースチューナーの選び方
形で選ぶ
- クリップ型:使い方はシンプルで、エレキベースのヘッドに挟んで使用します。比較的安価で手軽な分、ペダルやラック方に比べて少々壊れやすく性能も劣ります。
- ペダル型:シールドを通して使用するため、クリップ性に比べ音程の正確性が高いです。
- ラック型:ラックでエフェクターを組んでいる方には、ラック型のベースチューナーも。クリップ型やペダル型に比べ液晶が大きく表示されるためわかりやすいのが利点。
- 置く型:譜面台や平らな場所などに置いて使用するタイプのベースチューナー。スピーカーやマイクが本体に搭載されているものが多いのが便利なところです。
機能で選ぶ
また、ベースチューナーに搭載されている機能で選ぶのもひとつの方法です。
まだチューニングに慣れていない方は「ベースモード」が搭載されているベースチューナーを選んだり、半音下げチューニングをよく使う方は「フラットモード」が搭載されているベースチューナーを選ぶと使いやすいでしょう。
精度で選ぶ
ベースチューナーの精度も、選ぶ基準のひとつとしてぜひ持っておいていただきたい知識です。
チューナーの精度はだいたい±○セントといった形で表示されますが、この数値が小さければ小さいほど精度が良いことを表します。
大体のチューナーは±1セントの精度で作られていますが、より細かい精度のベースチューナーを使用することで「チューニングしたのになんだか合っていない気がする……」という悩みを減らすことができます。
ベースチューナーおすすめ14選
ベースチューナーの使い方
チューニングをする
ベースチューナーの最も一般的な使い方は、言わずもがなチューニングに使用することでしょう。
また曲によっては半音下げチューニングやドロップチューニングといった、レギュラーチューニングとは異なるチューニングに変えなければいけないこともあります。
そういった変則的なチューニングが必要な場合でも、ベースチューナーがあれば安心してチューニングできますね。
音感を鍛える
あとは音感を鍛えるというのも、ベースチューナーを使って行うことができます。
今ではYoutubeでも「ベース チューニング音」などと検索すればエレキベースのチューニング音が動画で出てきます。
時間があるときはそういった動画を参考に耳でチューニングしてから、答え合わせでベースチューナーを使ってみると音感が鍛えられていきますよ。
時と場合によって使い分ける
また時と場合によってベースチューナーの種類を使い分けるのも上手い使い方のひとつ。
筆者も日常の練習ではクリップチューナー、合わせや本番ではペダルチューナーといった感じで使い分けています。
ベースチューナーの代用品は?
アプリ

ベースチューナーを忘れてしまった場合などは、スマートフォンのチューナーアプリを代用する方法があります。
先にご紹介したPOLYTUNEにもアプリバージョンが存在し、他にはベース専用のベースチューナーアプリも。
ただしエレキベースの場合音が低すぎてスマートフォンのマイクでは拾えないことがほとんどのため、緊急の場合を除いてベースチューナーを使用することをおすすめいたします。
そして今やアプリをダウンロードしなくとも、検索エンジンのGoogleでチューニングが出来るようになりました。
方法はGoogleの検索画面で「Google tuner」と検索するだけです。
ただしこの方法でもマイクはスマートフォンに依存しますし音程の目盛りもかなり大雑把なため、ベースチューナーというには少し心許なさを感じます。
音叉
また、音感を鍛えるのに音叉を使用するのもひとつの方法です。
様々な音程の音叉が存在しますが、一般的なチューニングで使用されるのは440HzのAの音叉のため、3弦5Fのハーモニクスまたは開放の実音で合わせることが出来ます。
ただし音叉でのチューニングは初心者には少し難しく感じやすいので、ベースチューナーでチューニングに慣れてから挑戦できると良いですね。
耳
絶対音感がある方やプロのベーシストだと、音叉などを使わなくても耳でチューニングを合わせられるという方も。
ここまでできるようになるには相当の努力が必要ですが、耳で合わせられるようになればバンドや他の楽器と合わせた時に臨機応変に合わせやすくなります。
ぜひ日頃ベースチューナーでチューニングしている時から、音感を鍛えることを意識してみてくださいね。
まとめ
ベースチューナーは自分に合ったものを使うことによって、演奏の幅を更に広げることができます。
この記事を参考に、自分に合ったベースチューナーを見つけて、より素敵なエレキベースライフを送っていただけたら幸いです。
売れ筋ランキングも
チェックしよう!