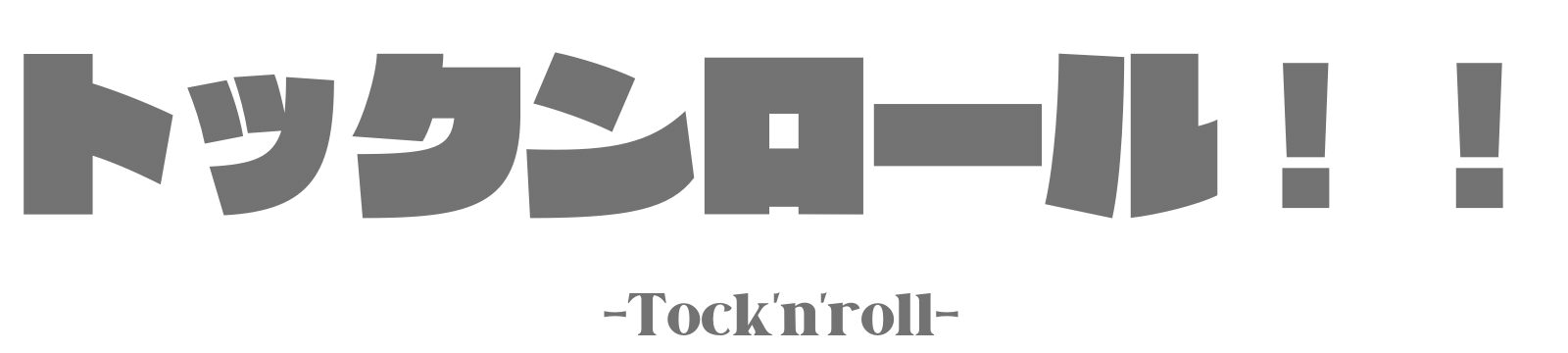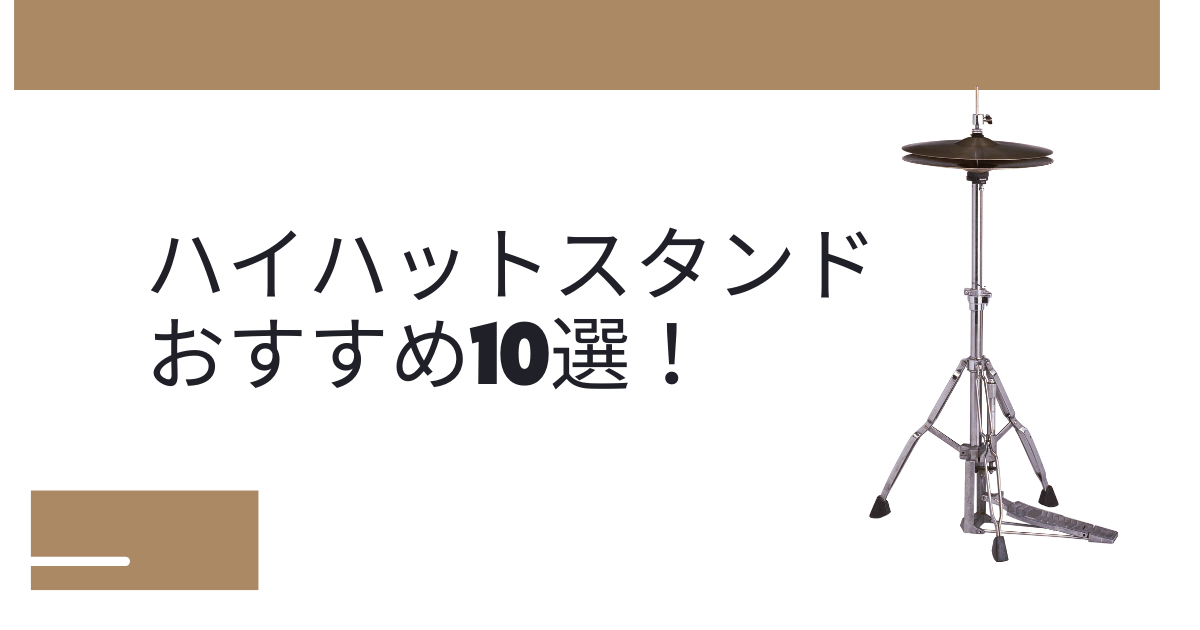ドラムセットの中でも特に中心となるハイハット・バスドラム・スネアドラム。
これらをまとめて3点セットとも呼びますが、その中でもハイハットシンバルを扱うために必要となるものが、今回取り上げるハイハットスタンドです。
「ハイハットスタンドなんて、ただハイハットを支えるためだけのものだ」と思っている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。
非常に重要なアイテムなのです。
そこで今回はハイハットスタンドのおすすめ商品10選を紹介し、組み立て方に関しても詳しく解説していきます。
ハイハットスタンドとは
ハイハットスタンドとは、文字通り「ハイハットシンバル」を「スタンド」させるためのハードウェアです。
ハイハットシンバルは2枚のシンバルを使用するという特徴を持っており、ハイハットスタンドがなければハイハットシンバルの音色を操ることができません。
なぜなら、ハイハットスタンドに付属している「フットペダル」で開け閉めすることで音色を操ることができる仕組みだからです。
ハイハットシンバルの開け閉めや、開け幅を調節するために左足を使うため、フットペダルが付いているのもこのスタンドの大きな特徴。
そのため、ハイハットスタンドを選ぶ上でペダルの操作性やカスタマイズ出来る幅も必要な項目となります。
また、スタンドを支えるレッグと呼ばれる、所謂足の部分にもさまざまな形状があり、多種多様な製品がラインナップされています。
ハイハットスタンドを購入する3つのメリット
現場トラブルが少なくなる
ライブハウスやスタジオに行けば備え付けのハイハットスタンドがあります。
一見、備え付けのハイハットスタンドを使用すれば良いと思いがちですが、そんなことはありません。
備え付きのハイハットスタンドは、様々な人が使用するためにパーツにガタがきていることも少なくありません。
「演奏中にハイハットスタンドのネジが緩んでしまった…」なんてことは日常茶飯事で起きるトラブルなので要注意。
そのため、自分でハイハットスタンドを持ち、しっかりと手入れを行うことで不必要なトラブルに悩まされることも少なくなります。
構造を知ることでトラブルに対応しやすくなる
ハイハットシンバルは、その機材の特性上非常に煩雑な作りをしています。
ハイハットシンバルを挟むための「クラッチ」、2枚のシンバルを開け閉めするための「センターシャフト」などがあり、他の機材と違って直感的に操作することがほぼ不可能なのです。
もしハイハットスタンドに何らかのトラブルが起きた時に、「対処方法が分からない…」ということもよくある話。
しかし、ハイハットスタンドを自分で購入し、扱いに慣れていると、自分の経験からトラブルを解決できることもあります。
自宅でハイハットの細かいニュアンスを練習できる
ハイハットは開け閉めの幅だけでなく、踏み込み具合などでも音が変わる繊細な楽器。
その微妙なニュアンスの違いを知るためにも、ハイハットスタンドを購入することは大きなメリットとなります。
なぜなら、自分のハイハットスタンドをもっていれば、踏み込み具合などを現場によって変える必要がないからです。
普段の感覚で音を鳴らすことが出来るので、表現にブレが出にくくなります。
ハイハットスタンドを購入する2つのデメリット
持ち運びが重い
ハイハットスタンドはスタンドのような金属類に加えて、フットペダルまで付いているので非常に重いです。
ドラマーは他にもフットペダルやスネアドラム、エフェクトシンバルなどを持ち込むことも多く、ただでさえ機材が多くなりがち。
そこにハイハットスタンドまで加わると、毎回持ち運ぶことはとても億劫なことになります。
ただ、その億劫さがドラマーの欠点とも言えますが、その苦労の分だけ良い音色で演奏できると思えば、デメリットではないとも言えます。
細かいパーツが多いため紛失・破損する
ハイハットスタンドは、細かいパーツが多いため、紛失・破損する可能性が高いです。
- シンバルを挟み込む「クラッチ」
- クラッチを取り付ける「センターシャフト」
- センターシャフトを覆うパイプ部分
- フットペダルが取り付けられた下部のレッグ部分
このように、ハイハットスタンドを分解すると点数が多く、特に「クラッチ」は小さい部品にもなるため、紛失のリスクも高くなります。
また、「センターシャフト」も金属で出来ているとはいえ、他の堅牢なスタンドよりは細いのが特徴。
持ち運び時に曲がったり、折れたりしてしまうリスクはあるので注意が必要です。
ハイハットスタンドの選び方
スタンドの安定感
ハイハットスタンドはフットペダルと同じく、足元に関わる機材になります。
そのため、ハイハットスタンドの安定感は、ハイハットスタンドを選ぶ際の大きなポイントの一つ。
なぜなら、足元がぐらついてしまえば演奏の安定感にも影響が出てしまうからです。
安定感を重視する際は、フットペダルにアンダープレートが取り付けられているものや、レッグ部分が「ダブルレッグ」と呼ばれる、二股に分かれているものを使用することがおすすめ。
ただし、安定感を重視すると重量が増すことや、ハイハットシンバル自体の音色が少しだけ損なわれてしまうというデメリットもあります。
ハイハットシンバル自体の音色への影響
ハイハットシンバルを直接取り付けるため、スタンドによって、ハイハットの音色に違いが出てきます。
まず、シンバルを叩くことでシンバルが揺れるのはもちろんですが、シンバルスタンド自体も若干揺れて音色にも影響することが考えられます。
シンバル本来の音色を活かしたいのであれば、なるべく軽量のものを選ぶのがおすすめです。
ツインペダルを使用するかどうか
ハイハットスタンドにも主に3タイプのレッグの種類があります。
- 2つの脚+ペダルで支える「2脚タイプ」
- 3つの脚+ペダルで支える「3脚タイプ」
- 地面に沿うような形で3つの脚が配置される「フラットレッグタイプ」
2脚タイプではツインペダルを置ける仕組みになっていますが、3脚タイプになるとその脚の部分を回転させることができるものとできないものがあります。
回転することが可能であればツインペダルを扱いやすくなるので、ツインペダルは使用できます。
フラットレッグタイプは、ツインペダルを置けないため使うことができません。
自分がよく使うフットペダルに合わせて選択することも必要になるのです。
フットペダルの使用感
バスドラムを操るペダルと同様、常に足に触れているのがハイハットスタンドのペダルです。
そのペダルの操作性が、ハイハットの音色にも大きく左右されます。
細かい表現をしたければ、それに対応できるような性能を備えたペダルの付いたスタンドを選ぶことが必須。
他にもスタンド自体の踏み心地、足を置いていても不安感のないサイズを選ぶことも重要になります。
ハイハットスタンドおすすめ10選
ハイハットスタンドの使い方
ハイハットスタンドは、下記の手順で使うことが可能です。
- レッグ部分を組み立てる
- センターシャフトを取り付け上部のパイプをセット
- ハイハットシンバルを取り付ける
- シンバルの開け幅を調整する
レッグ部分を組み立てる
ハイハットスタンドを使う際は、まずスタンドの土台となるレッグ部分を組み立てます。
脚が閉じられていることが多いので、ネジを緩めて脚を一杯まで広げます。
その後、ペダル部分のフープやアンダープレートを取り付け、ぐらつかないことを確認してからレッグ部分は組み立て完了。
センターシャフトを取り付け上部のパイプをセット
脚部にはセンターシャフトを取り付けるためのネジ受けが付いています。
センターシャフトにもネジ切りが付いているので、その二つを合わせて取り付けます。
そのセンターシャフトを覆うような形で上部のパイプを取り付けると、スタンド自体はほぼ完成です。
ハイハットシンバルを取り付ける
まずはボトム側のシンバルを上部パイプのシンバル受けに取り付けます。
この時、ハイハットスタンドにシンバル受けの角度を調整できる機能があれば、自分の好きな角度に変えることが可能です。
その後、トップ側のシンバルを、2本のナットからなるクラッチにシンバルに挟み込みます。
トップシンバルはナットに直接触れるようにするのではなく、フェルト同士ではさみ、その両側をナットで締めるようにしてください
そのクラッチに取り付けたシンバルを、センターシャフトへ通すことでハイハットスタンドは完成となります。
シンバルの開け幅を調整する
あとは自分で踏んでみて、2枚のシンバルの開け幅を自分の好みに調整します。
少しの力でスタンドペダルを踏みながら、クラッチに取り付けられたネジを閉め、センターシャフトへ固定させることで、開け幅が変わるという仕組みになっています。
まとめ
ハイハットスタンドはただハイハットを支えるだけでなく、その特性上、ペダルも付いており、複雑な構造をしています。
その分、ハイハットの無限の表現力を引き出すことに一役買うスタンドでもあるので、ぜひ色々試して、自分に合うものを見つけてみて下さい。
売れ筋ランキングも
チェックしよう!