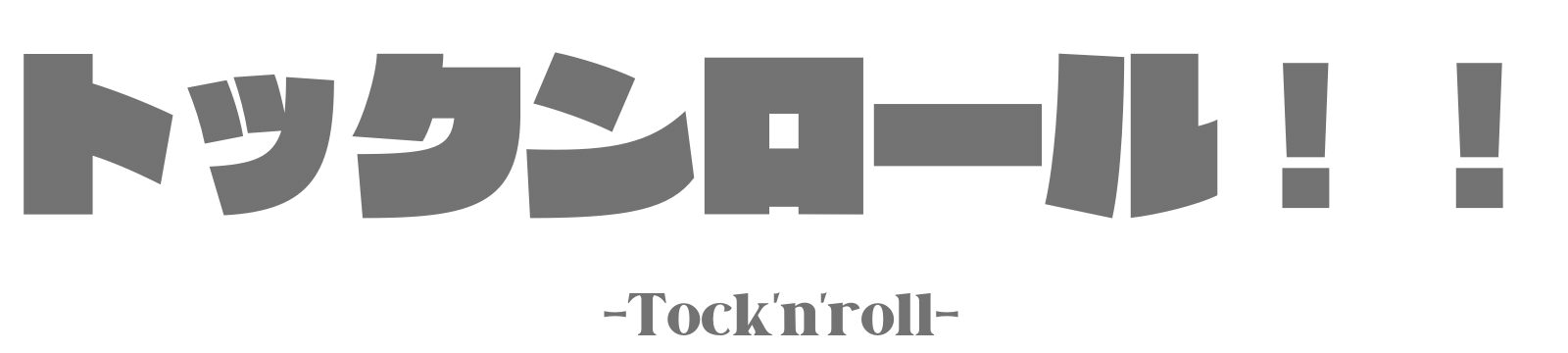スネアドラムの中にもさまざまなパーツがありますが、中でも重要なアイテムが今回紹介するスネアスナッピーです。
スネアドラムは太鼓類の中でも非常に特徴的な音色をしていますが、その音色の根幹にあるものがスネアスナッピーといっても過言ではありません。
スナッピーはスネアドラムの裏面ヘッドに直接触れるパーツだけあり、スナッピーを変えるだけで印象がガラッと変わることも少なくありません。
スナッピーにも材質やワイヤーの本数など、さまざまな違いがあるので、自分の目的とするサウンドになってくれそうなスナッピーを選ぶことが大切となります。
そこで今回は、スネアスナッピー(以下、スナッピーと呼びます)がどのようなものか、使い方からおすすめ商品までご紹介します。
スナッピーとは

スナッピーとは、スネアドラムの裏面ヘッドに装着されている響線の束のこと。
金属製のワイヤー数十本を、金属製のエンドプレートに取り付けたものであり、そのエンドプレートにはフィルムやワイヤーが付けられているアイテムです。
このフィルムやワイヤーをスネアドラムの「ストレイナー」と呼ばれる部分に装着して使用します。
スネアドラムに限らず、太鼓類を叩く時は表面のヘッドをスティックで叩くことになりますが、その表面の振動が裏面ヘッドに伝わり振動することで膨らみを持つようなサウンドが出ることが太鼓類の音が鳴る基本の構造です。
スネアドラムの場合は、裏面ヘッドにスナッピーが装着されており、裏面ヘッドが振動する際にスナッピーのワイヤーが震え、「ジャラッ」という音を加えることになり、スネアドラムらしい音になるのです。
スナッピーのサイズ
スナッピーのサイズは、お持ちのスネアドラムのインチに合わせる必要があります。
世に出ている7~8割のスネアが14インチのスタンダードサイズですので、ほとんどのドラマーさんが14インチに合うスナッピーを購入することになるでしょう。
もし、14インチより小さな口径のスネアドラムを持っている場合は、お持ちのスネアドラムと同じサイズのスナッピーを購入しましょう。
14インチ用につくられたスナッピーを、14インチよりも小さなスネアドラムに使用するとスナッピーがはみ出してしまい、本来の音を鳴らせなくなってしまいます。
スナッピーの音の高さ
スナッピー自体、ドラムの音の高さに影響を与えるようなアテムではありません。
スタンダードなスナッピーですと、24本のワイヤーがついているのですが、ワイヤーの数が少なくなると「ジャラッ」という音が少なくなります。
よりスナッピーの「ジャラッ」という音色を響かせたいのならばワイヤーが多めのスナッピーを選びましょう。
スナッピーにこだわるメリット
よりスネアドラムらしい音になる
前述した通り、スネアドラムを独特なサウンドたらしめているのがこのスナッピーですから、スナッピーを使うことで、よりスネアドラムらしい音になることがメリットです。
スナッピーを装着したストレイナーのレバーを切り替えることで、スナッピーを当てたり、反対に当てないようにすることが出来ます。
スナッピーを裏面ヘッドに当てない状態で演奏すると、他の太鼓類との違いがあまり無い音になってしまいます。
場面によってはそれも良い音色になりますが、やはり基本的にはスナッピーを裏面ヘッドにあてた状態で演奏するのが基本。
自分の目的にあったスナッピーを選ぶことで、より自分好みの音色で演奏でき、その高揚感がより良い演奏をもたらしてくれるでしょう。
スナッピーを使う際の3つの注意点
チューニングが難しくなる
ドラムという楽器は非常にチューニングが難しいことで知られています。
ヘッドを固定するためのテンションボトル付近の音程をそれぞれ一定にすることが基本になっていますが、スナッピーがあるとその音程が非常に分かりにくくなります。
軽く叩いても響線がなってしまい、そのたびにジャラッという音がしていては、なかなか正しいチューニングもできません。
チューニングをする際は、なるべくスナッピーを裏面ヘッドに当てない状態で行うことが望まれます。
現場で共鳴することが多々ある
裏面ヘッドが振動することで、それに接触しているワイヤーが震え、ジャラッという音がするというのは前述した通り。
しかし、これはスネアドラムの表面を叩いた時に限った話ではありません。
例えばライブハウスでライブをしている時に、ボーカルだけで歌うパートがあるとしましょう。
その時に、そのボーカルの声がスピーカーから出ることで、その空気の振動がスネアドラムの裏面に伝わり、ワイヤーが震えることがあります。
こういった場面でジャラジャラとワイヤーが鳴ってしまうと、バンド全体の雰囲気を壊しかねないことに繋がりますので、ワイヤーが震えるのは、スネアドラムを叩いた時だけでは無いということは、覚えておくと良いでしょう。
スナッピーの故障があった場合、裏ヘッドに傷がつく
スネアドラムを使用していて、急にスナッピーのワイヤーが1本だけエンドプレートから外れたり、切れたりしてまるでギターの弦が切れているかのような状態になることもあります。
そのような状態を放置しておくと、スネアドラムの裏面ヘッドを傷つけることとなります。
スネアドラムの裏面ヘッドは、スナッピーを響かせるために、非常に薄い作りをしていることが多いです。
切れたワイヤーを放置しておくと、その切れて鋭利になった部分が裏面ヘッドに何度も当たることで、破れたりということもあり得るので、スナッピーの調子は細かく確認しておくと良いでしょう。
スナッピーの選び方
ワイヤーの本数
スナッピーにも様々な種類がありますが、特に分かりやすい違いは、ワイヤーの本数になります。
一般的にはワイヤーの本数は20本となっていますが、中には42本と倍以上多いものもあったり、反対にワイヤーの数が少なかったりということもあります。
基本的にはワイヤーの数が少ないほど、太鼓本来の鳴りを活かすこととなり、反対に多ければ多いほどワイヤーの反応が良くなり、派手な音になっていきます。
派手な音になるというとロックな音を想像しますが、プレスロールなどを多用する、ワイヤーをしっかり鳴らしたいジャズなどでも使用されることもあります。
スナッピー固定部
スナッピーをスネアのストレイナーに固定するためには、ストレイナーとスナッピーを繋ぐ部位が必要です。
その部分が、フィルムテープか、コード式になっているかも選ぶ際の重要なポイントです。
フィルムテープの場合、まず、スネアへの着脱が圧倒的に楽に出来ます。
さらに耐久性もあり、滅多に切れることもありませんが、デメリットとしては、若干音がミュートされることにあります。
反対にコード式は着脱が少し手間がかかる、耐久力もフィルムテープには劣るが、楽器本来の鳴りを活かすことができます。
材質について
響線となるワイヤーの素材からも、音色の違いが現れます。
現在販売されているものでは、スチール素材が大半を占めていますが、他にもブラス材、ステンレス材、ブラス材などが存在します。
ワイヤーを取り付けるエンドプレートもまた、上記のように使われている素材がモノによって違います。
一般的に新品のスネアにはスチール材のスナッピーが取り付けられていることが多いですので、そこから様々な商品を試し、音色の違いを確認すると良いでしょう。
スネアの口径にあっているかどうか
スナッピーはスネアドラムに取り付けるため、そのスネアドラムの大きさに対応するものでなければ、装着できません。
スネアドラムはほとんどが14インチですが、13インチのものなどもあります。
自分が所有するスネアの口径を確認し、スナッピーが対応する大きさのものなのかよく確認することが大切です。
裏面ヘッドの当たり方の違い
裏面ヘッドへの当たり方の違いによってもスナッピー選びは異なります。
ただ、市場に出回っているほとんどのものが、スナッピーのエンドプレートも裏面ヘッドに当たる、内面当たりと呼ばれる商品です。
全面当たりはスネアに特殊な加工が施してあるため、全面当たりのスナッピーを使うことを指定されています。
構造上、裏面ヘッドだけでなく、スネアのシェル自体にもワイヤーが触れるので、ダイレクトに振動が伝わり、レスポンスが早く、ハッキリした粒だちの音になりやすいです。
スナッピーおすすめ10選
スナッピーの使い方
スネアのストレイナーをオフの状態にする
まずはスネアのストレイナーをオフの状態になっているかを確認します。
ストレイナーにレバーが付いているので、それを下げればオフの状態になります。
もしストレイナーがオンになっている状態でスナッピーを装着すると、裏面ヘッドにスナッピーが当たらない状態になり、装着し直しとなることもあるので、しっかりと確認しましょう。
裏面ヘッドにスナッピーを当てる
次に、裏面ヘッドにスナッピーを当てて、位置を調整します。
この時に、調整レバーが付いているストレイナー側の隙間を反対側よりも少し開けておくのがコツです。
スナッピーはストレイナーのレバーをオンにした時に、裏面ヘッドの中心に位置しているのが理想です。
ストレイナーをオンにする時に、若干レバー側へ引っ張られることになるので、装着時には少し隙間を空けておくと、演奏時には裏面ヘッドの中心に位置することとなります。
固定用のフィルムテープorコードをストレイナーに取り付ける
スネアのストレイナーは、スナッピーを固定するだけの部位と、スナッピーの着脱、調整ができる部位が、両側2つに分かれています。
ストレイナーはテープかコードをテンションボルトで固定できるようになっているので、その部分に固定するテープかコードを通して、ボルトを締めて固定します。
もしスナッピーを強く引っ張りすぎていたり、緩く張りすぎたりしてスナッピーが上手く裏面に当たらない時は、ここを調節して調整します。
ストレイナーをオンにする
スナッピーを取り付けたら、ストレイナーのレバーを上げて、スナッピーを裏面ヘッドへ当てます。
ここでスナッピーが上手く当たらないときは、先ほどテンションボルトで固定したコードかテープを緩めたり、引っ張ることで、調整が可能です。
ストレイナーのつまみを調整し、好みの音にする
ストレイナーに調節ノブが付いていますので、その部分を回して、スナッピーの当たり具合を調整します。
スネアの音が詰まり気味だなと思ったら、スナッピーによって裏面ヘッドがミュートされているとのことですので、緩める方向に回します。
逆に、スナッピーがジャラジャラと言い過ぎている時は、響線に浅くしか当たっていないということなので、締める方向に回します。
まとめ
スナッピーはスネアドラムのサウンドの核を担うと言っても過言ではない商品です。
それだけに様々なニーズに応えられるよう、多種多様な種類があり、迷ってしまうことも多いと思います。
ですが、スナッピーはそんなに高価な製品ではなく、それでいて劇的に音が変化します。
まずは先程紹介したおすすめ10選の中から一つでも選んで試してみてはいかがでしょうか。
きっと新たなサウンドに心惹かれ、よりドラムが楽しくなることでしょう。
売れ筋ランキングも
チェックしよう!